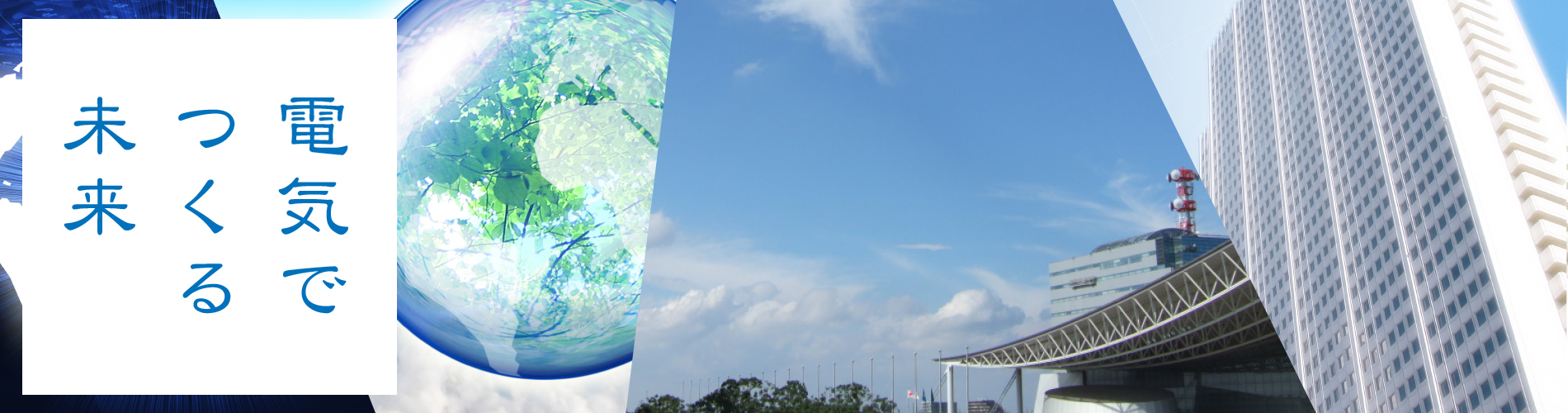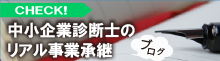前回からのつづき
NHK朝ドラあんぱんが最終回を迎えました。ドラマの時系列によると、私はちょうど絵本あんぱんまんの第一世代のようです。小学校1年生で転校した先では、一部の友達があんぱんまんの話で盛り上がっていました。当時は転校生だから知らないのかと少し寂しく思っていましたが、今思い返すとそれは押し並べて隣接する市立保育所の出身者。ドラマのような読み聞かせがそこで行われていたのでしょう。ちなみに私の幼稚園は「おしいれのぼうけん」でした。
その後小学校の図書館で絵本を読み、高校時代から始まったTV放送を見て、中小企業診断士として行う企業研修では主題歌の歌詞を引用するなど、何かとアンパンマンにはお世話になり、ドラマも途中から見るようになりました。
ドラマのテーマは「逆転しない正義」。今年はちょうど戦後80年、この言葉が様々な場面で重みをもって受け止められています。正義は時にあっけなく逆転します。そして今、我が建設業技能労働職の世界でも正義を逆転させようとする動きが起きています。
改正建設業法 当局説明会
2025年8月から9月にかけて、改正建設業法12月全面施行に向けての説明会が全国10カ所で開催され、私もwebから参加しました。配布資料は「労務費の基準について」。建設技能者の不足、高齢化に危機感を抱いた国は、これに対処すべく近年数次にわたり建設業法を改正しています。我々業者には「担い手の育成及び確保(同法第25条の27第1項)」を責務として課し、現場で手を動かす技能労働者の処遇改善を求めています。そしてついに今年、かねて予告されていた職種別、レベル別の標準労務費を公表、勧告した上で、従来元請のみに課していた「著しく低額な労務費による見積依頼の禁止」について一歩踏み込み、下請に対しは原価割れ契約の締結自体を禁止します。
ここまでは、下請当事者として心強い限りですが、各論を見ると、以前公表された内容からは幾分後退し、雲行きが怪しくなってきます。形式を備えればあとは勝手にうまくいく、とは霞が関も考えてはいないでしょうが、これまで優越的地位の濫用の放置があまりにもひど過ぎました。資料第6章では「実効性の確保」として種々の対策を列挙していますが、たとえば元請事業者による手のひらを返したような字面だけの「コミットメント」を、これまで忍従を強いられ続けた下請が素直に信じることができるでしょうか。いざ法令やガイドラインに促されて条件交渉の場を設けても、対面する担当者は変わりません。そして長年続く力関係のひずみで、下請には拘禁症状が現れます(私もその一人で、本ブログもその発露かも知れません)。また、改正内容を論じた第3,4章のまとめには、「『上位注文者から一方的に提示された金額で契約締結する』商慣行を改め」とありますが、この商慣行自体が現行法規でも明確な違反であり、図らずも長年当局がこれを追認してきた事実を暴露しています。資料の最後にご意見の問合せ窓口が記されていたので、当事者の声としてコメントを送信しました。回答は一括公開とのことですが、果たして取り上げてもらえるでしょうか。
さて、本説明会を開いた本省不動産・建設局建設振興課担当各位のお仕事としては、この法施行で一段落でしょう。しかしこれによりその先の各地方整備局建政部担当課に所属する建設Gメンが、本説明資料でうたう「正義の味方」のように下請業者を助けてくれると考えるのは、あまりにも楽観的でしょう。結局は権利の上に眠るものは保護に値せずという法格言を肝に銘じ、技能労働者たる当社従業員の権利を(当人たちからウザがられても)守るのが建設業経営者の使命、と腹をくくるしかなさそうです。
正義が逆転するとき
正義の反対は別の正義といわれます。私自身、下請職人の家庭で育ち、運賃というキャッシュフローが途切れない鉄道会社や金融手法を駆使する不動産投資ファンドで「お金を使う仕事(インベストメントセンター)」に従事し、また下請に戻ってきました。それぞれの仕事では価値観も、正義も全く違います。
下請のカウンターパートは当然ながら元請の工事業者管理部門。分かりやすいKPIは原価低減でしょう。これに最も即効性のある手法は下請たたきです。どうひいき目に見ても、その企業内において花形部門ではありません。社内で傍流として疎んじられれば、社外にもそれ求めます。そして下請はこれを「喜んで受け入れるのが仕事」という世界観。建設業法よりも、上司の顔色が判断基準。書いていて思い返しました。あ、これは20代の自分が見た景色?
商業施設勤務時代、バブル崩壊後の売り上げ不振について経営者でもある自営業テナントの店長から図星を突かれた時、勤務先の企業方針を公式見解として苦しい言い訳をしていました。一方、本社に勤める多くの先輩、上司は企業間の力関係でねじ伏せる伝家の宝刀を体得し、人によってはこれを常時発動しています。この違和感の正体に気付いたとき、私は「育ちが違う」ことを自覚しました。
時は下って当社に入りリアル半沢直樹事件の頃、元請の理不尽な要求に嬉々と従う母親やベテラン従業員に強く不満を持っていましたが、彼らもあの世界観で生きています。文学者で武道家の内田樹氏は著書日本辺境論で水戸黄門を例にとり、日本人の辺境性という切り口でこれを考察しています。偉そうな態度を取る人を無批判に偉い人と認識し、その空気に盲従することで和を保つ。そしてこの長いものに巻かれ、ゆえにだれも責任を取らないメンタリティは日本人および日本語と一体不可分とのこと。今この場でこれを逆転させるには水戸黄門よろしく自らが権威になるほかありませんが、建設業において「下請」というカーストラベルは、これを許さない程に十分強固です。
そして誰もいなくなる?
では、いつこの世界観が逆転するのか。結局は業界に誰もいなくなったときでしょう。今日もどこかで行われている締切間際の工事現場は、ドラマ「あんぱん」に見る戦争さながら。工期厳守が絶対的な正義であり、大本営(元請)が施主の都合を忖度して作成、破綻した工程の厳守こそが最大の正義である、と信じ込まされる下請技能労働者は、不眠不休で働きます。元請から称賛は受けられますが、金銭的な報酬は、、そもそも予算がありません。働き方改革が一般に市民権を得た現在、元請がうたう「コミットメント」により、ついに建設業においてもこの世界観は終焉を迎えたかのようです。でも実際の現場末端の空気までが変わるには、人の完全入れ替えを待つ必要がありそうです。工事下請契約には下請に屈辱を与える権利が内包されると刷りこまれた元請末端担当者は、今も厳然と存在します。契約締結権者としては、このにおいを契約書類からかぎ取り、近付かないことこそが何より重要で、従業員を守るためにできる最大の役目です。
「良いお金をもらうには、人ができないことか、やりたくないことを代わりにしてあげる」は中小企業診断士として到達した私の持論ですが、建設技能職の評価(収入)が低いのは3K(きつい、汚い、危険)に加え、日曜大工レベルの認識で「所詮は誰でもできる簡単な仕事」と思われていることが一因のように感じます。では、仮に技能労働者が絶滅し、例えば電気配線は全て自分で行う世界になったら、どうでしょう。中学理科を習得していれば、自分で調べてできるでしょう。手先が器用な人は、他人の分も代行して対価を得るでしょう。一方で、労働者に指示することが自分の仕事という自意識の人は、獲物が絶滅した捕食者のような末路をたどることになるかも知れません。
同業者にこの建設業絶滅話をしたら「終末思想」とドン引きされましたが、国土交通省が提唱する建設業の新4K(給料が良い、休暇が取れる、希望がある、格好いい)は、ここに至って初めて実現するように思えてなりません。
なお、現在「人ができないことをやって稼ぐ」の最先端であるIT業界は、AIによってあと数年で「誰でもできる簡単な仕事」に変容すると予測され、ニューズウィーク日本版によると学生の就職活動にもすでに影響が出ているとのことです。米トランプ政権はこれを見据えてエリート大学への補助金を削減し、電気技師や配管工を育てる職業訓練校に投資するようです。
事業承継から11年。やっと時代が自分に追いつきました(笑)。